    |
|
|
ホーム>薬の常識>薬の効果と副作用を知っておこう!
|
|
|
 |
|
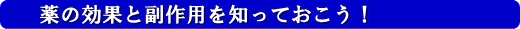
| |
薬を服用すると、体の中で様々な反応が起こり、病気の症状が和らいだり、原因が除去されたりして病気が回復の方向に向かっていきます。このように、細胞や臓器の機能に影響を与えて、体の機能を修飾する、体に対する薬のはたらきを、薬理作用といいます。

薬理作用には様々な種類があり、主作用と副作用もその一つです。薬とは、病気の改善や予防のために投与されるもので、そのために有用と考えられる薬理作用を主作用、期待する治療効果以外の薬理作用を副作用といいます。従って、言葉の意味だけとれば、副作用というのは、すべて悪い作用、というわけではないことになります。
実際、そうではありません。例えば、花粉症の方が抗ヒスタミン薬を投与されると鼻水は止まりますが、同時に眠くなるという副作用があります。眠気は仕事をする人や車の運転をする人にとっては都合の悪い作用です。しかし、眠りたい人にとってこれは好ましい主作用になります。事実、睡眠導入剤の一般用医薬品として抗ヒスタミン薬が販売されています。この例のように、副作用が主作用となるケースもあるのです。
とはいっても、多くの場合この副作用は望ましくない有害な作用となるため、本来同一の概念ではないのですが、有害作用とほぼ同義語のように用いられます。

治療係数とは、安全域とも呼ばれ、くすりの安全性を示す指標として用いられます。ある集団の50%の被験者が薬物に反応する用量を50%有効量、最大有効量を超えてさらに用量を増やした場合に50%の被験者が死亡する用量を50%致死量といい、
50%致死量/50%有効量=治療係数
という関係になります。これら二つの数字の差が大きければ、その薬は有害作用(副作用)が発現しにくく、安全性が高いといえますが、差が小さければ、有効量と致死量が接近しており、血中濃度を測定しながら適切な用量を決めていく必要があるため使用が難しい薬だといえます。
(最近では、動物愛護の観点から致死量を求めないことも多く、致死量の代わりに中毒量を用いることも多いです。)これらの数値を元に、投与する量などが決められています。

薬が投与され薬理作用を示すには、くすりが作用部位まで到達しなければなりません。多くの薬において、薬理作用の強さとその持続時間は、その薬が作用する場所での薬の濃度と滞在時間に比例します。その濃度を決めるのは、薬の吸収、分布、代謝、排泄などです。
これらは個人個人によっても、年齢や性別、心理状況によっても異なるので、同量の薬を服用しても、効果がある人もいれば、全く効かない人もいます。同じように、副作用の出現にも個人差があります。
この個人差の起こる原因の一つに、遺伝的要因が挙げられます。ヒトゲノム計画によって全塩基配列が解明され、それに伴って人の薬に対する反応性に大きな個人差があり、これに遺伝的要因が関与していることが分かってきたのです。
今後、さらに詳しい解明が進めば、先ほど述べた治療係数も集団においてではなく、その人自身に合った数値が導き出されるかもしれません。そうなれば、副作用を心配することも少なくなります。これからは、患者さん一人一人に最も適している治療を行うオーダーメイド治療が増えてくるかもしれませんね。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright(C) これであなたも医の達人 All Rights Reserved. |
|



