    |
|
|
ホーム>薬の常識>薬を飲むと眠くなる理由とその対処法
|
|
|
 |
|
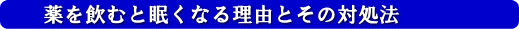
| |
薬を飲んだら眠くなってしまい、車の運転などで危ない思いをした、という方も多いのではないでしょうか?
まずは、眠くなってしまう薬をまとめて紹介します。
三環系および四環系抗うつ薬や、抗精神病薬などの脳の病気の治療薬には、脳の働きを抑えるため眠気の副作用が現れます。
同様に、パーキンソン病やむずむず脚症候群の治療に使われるドパミン受容体作動薬は、眠気を感じていなくても突然眠ってしまう「睡眠発作」を起こすことがあるため、内服中は安全を考慮して、車の運転などの危険を伴う作業は避けるようにしましょう。
脳に作用する薬ではないですが、副作用として眠気を起こすことがある薬として一番有名なのは、抗ヒスタミン薬です。市販の風邪薬や花粉症のときに飲む薬として、一番身近な薬なのではないかと思います。
また、睡眠薬の効果を増強する薬もあります。薬の血中濃度が高くなり、効果や副作用が強く出てしまう薬には、抗真菌薬やマクロライド系抗生剤などがあります。アルコールとの同時摂取によっても薬の作用が強められてしまうことがあるので、注意してくださいね。
さらにナルコレプシーなどの過眠症の治療には、醒維持薬(中枢精神刺激薬)が用いられ、これらの服用を急にやめると反動で強い眠気に襲われます。ですから病気が良くなっても、自己判断で薬を中止せず、必ず主治医の指示に従って薬を減らしていくようにしましょう。

ここでは馴染みのある、抗ヒスタミン薬について説明します。
ヒスタミンはアレルギー症状の原因物質です。花粉などのアレルギーの原因物質が鼻に入ると、鼻の粘膜ではヒスタミンが作られて体内に放出されます。これが同じく鼻の粘膜にある「H1受容体」という部分と結合すると、くしゃみや鼻水といったアレルギー症状を発現します。
「ヒスタミン」と「H1受容体」との関係は、「鍵」と「鍵穴」の関係に似ています。鍵が鍵穴にぴったりはまるように、「ヒスタミン」が「H1受容体」にぴったりはまればアレルギー症状が発現するのですが、抗ヒスタミン薬は、ヒスタミンが結合する前に鍵穴であるH1受容体をふさぐので、ヒスタミンが放出されてもH1受容体と結合できなくなりアレルギー症状の発現を抑制することができるのです。
ところが、一部の抗ヒスタミン薬は脳の中にも移行し、脳内にある「H1受容体」もブロックしてしまいます。
脳内でのヒスタミンの役割はアレルギー症状の発現とは無関係で、集中力・判断力・作業能率や覚醒の維持に関与しているため、そこに抗ヒスタミン薬が入ると、同じメカニズムで脳内のヒスタミンの働きも妨げられてしまうのです。
その結果、ヒスタミンが脳の中でも働くことができずに、眠気や判断力の低下を引き起こしてしまうのです。専門家からは、一部の抗ヒスタミン薬を服用した際には、グラス4杯分のウィスキーを飲んだのに相当する程能率が下がるとも指摘されています。

大事な会議や受験の前、車を運転する時など、眠気や判断力の低下があらわれては困る場面ってありますよね。そのようなときは、抗ヒスタミン作用のない薬や、第2世代抗ヒスタミン薬を使用するようにしてください。
抗ヒスタミン作用のない薬には、パブロン50や改源、葛根湯などがあります。改源や葛根湯は生薬であり、東洋医学の漢方薬として知られています。
一般的に西洋医学的な薬は、特定の原因を完全に食い止めようとしてしまうあまり身体全体のバランスを崩してしまい、他の部分で支障をきたしてしまうことが多いです。抗ヒスタミン薬も同じですね。そうした反省から、近年では東洋医学が注目されています。東洋医学では、原因を解消することよりも身体全体のバランスをとることを重視します。
しかし先ほど述べた3つの薬には抗ヒスタミン作用がないため、くしゃみや鼻水、鼻づまりには当然効果は見込めないことを理解しておく必要があります。
一方、第2世代抗ヒスタミン薬というのは、第1世代抗ヒスタミン薬に比べて眠気などの副作用を起こしにくいよう開発されたものです。抗ヒスタミン薬は脳内に入り込んでH1受容体をブロックするため、そもそも抗ヒスタミン薬が脳内に入り込まないようにしようというのが第2世代抗ヒスタミン薬の狙いです。
第2世代抗ヒスタミン薬は、服用により脳内のH1受容体が50%以上ブロックされるものを鎮静性タイプ、20%〜50%のものを軽度鎮静性タイプ、20%以下のものを非鎮静性タイプとして、3つに分けられます。非鎮静性の抗ヒスタミン薬の成分は脳に入りにくいため、服用しても脳内のヒスタミンとH1受容体の結合を妨げることがほとんどなく副作用が現れにくいので、現在のアレルギー治療の主力となっています。
眠くなる副作用とはなんとも厄介なものですが、薬を飲む時間、間隔、量はよく理解し、不安になって自分の判断で薬を飲むのを止めてしまったり量を加減したりして、かえって病気を悪化させることのないようにしましょう。
医療の進歩により副作用の起こりにくい薬も開発されているので、薬と上手に付き合って快適に毎日を過ごしたいですね。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright(C) これであなたも医の達人 All Rights Reserved. |
|



