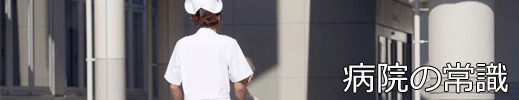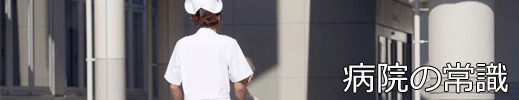日本における救急医療体制は、都道府県が作成する医療計画に基づいており、「重症度」に応じて初期(第一次)、第二次、第三次救急医療の3段階体制をとっています。
また、救急指定病院もこれらの段階のうちどの段階まで対応するか想定した上で患者受け入れ体制をとっています。

入院治療の必要がなく、外来で対処しうる帰宅可能な軽症患者に対応する救急医療。
各都道府県で数ヶ所ずつ設置されている「休日夜間急患センター」「救急(休日)歯科診療室」のほか、その日の在宅当番になっている当番病院・診療所が対応します。

入院治療や手術を必要とする重症患者に対応する救急医療。
病院群輪番制(いくつかの病院が当番日を決めて救急医療を行う)に参加する病院が順番で、夜間および日曜、祝日、年末年始などの診療を行います。
ほかにセンター方式/共同利用型病院(中核となる救急指定病院に当番で他の病院や開業している医師が集まり、休日や夜間の救急医療に当たる方式) があります。

二次救急まででは対応できない一刻を争う重篤な救急患者に対応する救急医療。
三次救急では複数診療科にわたる特に高度な処置が必要であり、「救命救急センター」や「高度救命救急センター」が対応します。
ちなみに「高度救命救急センター」とは「救命救急センター」のうち特に高度な診療機能を有するものとして厚生労働大臣が定めた医療機関のことをいいます。

|
|
|
|