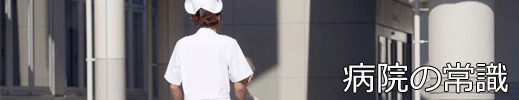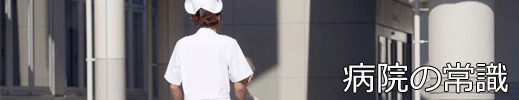内科、皮膚科、神経科といった形で医療機関が都道府県に届出をし、看板や電話帳などに記載している診療科を「標榜科目」といいます。
表示してよい診療科は、医療法第70条、医療法施行令第5条の11で定められている次の38の科に限られています。
| 医 業 |
| 内 科 |
心療内科 |
精神科 |
神経科 |
神経内科 |
| 呼吸器科 |
消化器科 |
胃腸科 |
循環器科 |
アレルギー科 |
| リウマチ科 |
小児科 |
外 科 |
整形外科 |
形成外科 |
| 美容外科 |
脳神経外科 |
呼吸器外科 |
心臓血管外科 |
小児外科 |
| 皮膚泌尿器科 |
皮膚科 |
泌尿器科 |
性病科 |
肛門科 |
| 産婦人科 |
産 科 |
婦人科 |
眼 科 |
耳鼻咽喉科 |
| 気管食道科 |
放射線科 |
リハビリ
テーション科 |
|
|
| 歯科医業 |
| 歯 科 |
矯正歯科 |
小児歯科 |
歯科口腔外科 |
個別に厚生労働大臣の許可を受けた場合のみ
標榜することができる診療科名 |
| 麻酔科 |

しかし、驚く人も多いと思いますが、なんと医師免許さえあれば麻酔科以外の何科でも自由に標榜することができるのです(ちなみに、麻酔科の医師は麻酔科標榜医の資格をとらなければ麻酔科医をなのることができません)。
例えば、産婦人科で長年働いてきた医師が、産婦人科、内科、小児科クリニックを開業したり、外科で手術ばかりしてきた医師が、内科を開業したりすることもめずらしくありません。
診療所を開業するにあたり、都道府県の許可を得なければいけないのですが、そこで専門医の資格や治療実績、経歴などは問われないのです(実はここが日本の医療の問題点なのです。アメリカなどでは標榜科目を掲げるには、専門医として所定の研修を受ける必要があり、医師免許も更新制になっています)。
よって、開業医にかかるときは、医師の治療実績や以前勤めていた病院、専門分野などを知っておく必要があります。
自分の身を自分で守るためには、それなりの知識と努力が必要です。
| 2008年の医療法改正により、一人の医師につき主たる診療科は二つしか表記できないように変更となりました。 |
|
今まで一人の医師で二つ以上の標榜をかかげていた病院・診療所には変更の義務はありませんが、2008年4月以降に新しく病院・診療所を開設する際には適応されます。

|
|
|
|