    |
|
ホーム>感染症情報>EBウイルス 検査と診断
|
|
 |
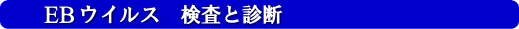 |
|
1週間以上つづく発熱、発疹、リンパ節の腫脹、扁桃痛などの症状があらわれると血液検査を行います。EBウイルスに感染すると血液中の白血球数が増え、その中に特徴的な異型リンパ球が見られるようになります。
また血液中のEBウイルスに関連する様々な抗体を詳しく検査することで、EBウイルス感染症の確定診断と病状の進行具合の確認の決め手となります。
それでは次に具体的な抗体検査について説明していきましょう。

ここからは少し専門的な話しになりますがご容赦下さい。
EBウイルスに感染した初期の段階ではVCA-IgMという抗体とEA抗体が陽性を示しますが、次第に陰性を示すようになります。
EBウイルスは潜伏期間が4?6週間と比較的長いため、症状が出て血液検査をした場合、この二つの抗体は陰性を示している可能性が高くなっているはずです。
この時、もしどちらかの抗体が陽性反応を示している時には、感染初期状態か急性増悪(感染が急激に広がっている状態)を示す根拠となります。
次にVCA-IgG抗体が陽性でEBNA抗体も陽性だと、急性感染を引き起こしたが現在は治癒した状態と判断されます。
したがってVCA-IgGとEBNA抗体の両方が陽性で何かしらの症状が出ている場合には、違う病気の可能性が高まったということになりますね。
しかしVCA-IgG抗体が陽性でもEBNA抗体が陰性の場合には慢性活動性EB ウイルス感染症が強く疑われることとなり、異型リンパ球の検査結果、問診と頸部腫脹の触診などと合わせて確定診断となります。
抗体とは異物に対して免疫機能が作り出すワクチンのことです。
したがって抗体反応が陽性ということは、過去に異物の侵入があったがそれを攻撃する抗体を作り出すことに成功しているということを意味しています。

EBウイルス感染症に対する特効薬は、残念ながら今の所開発されていません。
発現している症状を抑える対症療法と、合併症を予防する治療がメインとなります。
この時、複合感染を防ぐ目的で抗生剤や抗菌剤が投与されることがありますが、ペニシリン系の抗菌剤は発疹が出るため禁忌とされています。
このように現状では慢性活動性EBウイルス感染症を発症した場合の治療は困難ですが、日本人の約8割の人はこのウイルスに対する抗体を生まれつき持っているといわれています。
したがって乳幼児期に感染しても、感染初期に熱が出る程度でその後自然と治癒していき、感染そのものにも気がつかないケースが多いのです。

現在健康診断で行う血液検査では、EBウイルス関連の抗体を調べる検査が含まれています。
この時検査結果でEBウイルス関連抗体反応が陰性の人は感染の可能性が高いということになりますので、キスや飲み物の回し飲みなどを出来るだけ避け、生活習慣を改善して、免疫力を弱めないようにしてウイルスに負けない体作りをするなど予防に努める必要があります。
EBウイルス感染症の初期症状は風邪と良く似ているため、風邪気味の場合は無理をせずに、病院で診察を受けるようにしましょう。

EBウイルス感染症にかかって一番ダメージを受けやすいのが肝臓です。
肝臓がかかる病気には、肝機能障害、肝硬変、肝不全、肝がん、慢性肝炎、ウイルス性肝炎などがあります。
この中でウイルス性肝炎に関してはA型、B型、C型などの肝炎を引き起こす肝炎ウイルスによるものと、EBウイルスやサイトメガロウイルス、ヘルペスウイルスなど肝炎ウイルス以外のウイルスによる肝炎とがあります。
EBウイルス感染症を基礎疾患とする肝炎や肝硬変の場合、具体的な治療法は今の所ありません。
それは慢性活動性EBウイルス感染症に対する特効薬が存在していないため、EBウイルス感染症が完治しない限り、肝炎を再発するリスクは常について回るからです。

肝炎を引き起こした場合は、とにかく安静にして飲酒や喫煙、寝不足、暴飲暴食などを避けて肝臓に負担のかからない生活習慣に改め、症状の進行を出来るだけ遅らせるというのが治療のメインとなります。
特に食生活は肝炎治療にとって重要となります。
しかしこれも肝炎の状態によって食事内容が変化してきますので、医師と相談の上、適宜食生活の改善を行う必要があります。
ただ、EBウイルスと性質の近いとされるサイトメガロウイルスやヘルペスウイルスに対する抗菌剤がEBウイルス感染症の治療に効果があったという報告例もありますが、今の所研究段階ですので、今後の研究成果に期待したいところです。

|
|
|
| 最新ノロウイルス情報→ |
|
|
|
Copyright(C) これであなたも医の達人 All Rights Reserved. |
|



