    |
|
ホーム>感染症情報>感染症情報>ノロウイルスと牡蠣(かき)の関係
|
|
 |
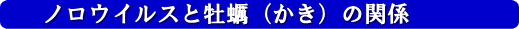 |
|
毎年寒い季節になると、「ノロウイルスの集団感染」、「ノロウイルスが大流行」などのニュースを耳にしませんか?
ノロウイルスは、感染力が非常に強いことがが特徴で、牡蠣などの二枚貝からの感染以外に感染者の吐瀉物からも感染しますし、吐瀉物の処理が不十分だと、そこからノロウイルスが舞い上がり、そのウイルスを吸い込んで感染するケースもあり、1人がノロウイルスに感染すると、家族全員がノロウイルスに感染することも珍しくありません。
ノロウイルスに感染すると、嘔吐や下痢、発熱の症状が現れ、場合によっては1日中トイレから離れられないほど症状が強く現れる場合があり、脱水症状などに注意しなければいけませんが、ほとんどの場合1〜2日で症状は治まり、快方に向かいます。

ノロウイルスの原因は、生牡蠣であると聞いたことはありませんか?なぜ、生牡蠣を食べると、ノロウイルスに感染するのでしょう?
ノロウイルスは、もともと牡蠣に生息しているわけではなく、海水に生息しています。そのため、海水を大量に飲めば、牡蠣を食べなくてもノロウイルスに感染するリスクはあるのです。
では、様々な海産物がある中で、なぜ牡蠣がノロウイルスの原因とされているのでしょう?
牡蠣は二枚貝に分類されます。二枚貝は、海水の取り込みと吐き出しを常時行っているため、二枚貝の中(中腸腺という内臓)にノロウイルスがどんどん蓄積され、濃縮されていくのです。
二枚貝には、牡蠣のほかにアサリやハマグリ、ホタテ、ムール貝などがあります。でも、ほかの貝類がノロウイルスの原因になるとは聞きませんよね?
牡蠣やホタテ以外の貝類は生で食べることはありませんし、ホタテは生で食べても貝柱の部分のみで、内臓部分を食べることはありませんので、同じ二枚貝で貝の中にノロウイルスが生息していても、ノロウイルスに感染するリスクは非常に小さいのです。

ノロウイルスは、なぜ寒い時期に流行するのでしょう?それは、牡蠣を良く食べる時期が冬だからです。
生牡蠣の旬は10月から4月とされています。冬に生牡蠣を食べることはあっても、夏に生牡蠣を食べる機会は少ないですよね。そのため、ノロウイルスは寒い時期に流行しやすいのです。
また、ノロウイルスの特徴として、気温が低ければ低いほど生存しやすいという点があります。また、冬は空気が乾燥していますので、空気が乾燥していると吐瀉物などに含まれるウイルスが空気中に舞い上がり、感染が広がりやすいんです。

生牡蠣を食べても、いつもノロウイルスに感染するとは限りませんし、一緒に食事をして生牡蠣を食べたのに、牡蠣にあたる人とあたらない人がいますよね。なぜ、そのような差が出るのでしょう?
それは、牡蠣に含まれるノロウイルスの量とその人の体調によります。全ての牡蠣が同じ量のノロウイルスを含んでいるわけではなく、生育過程や環境によって、ノロウイルスの量が違ってきます。
ウイルス量が少ない場合、体内にノロウイルスが入っても、症状が出ないこともありますし、、生牡蠣の中でも1〜2%はノロウイルスに汚染されていないものもあります。
また、免疫力が強ければ、少量のノロウイルスが体内に入っても、免疫システムがウイルスに勝つこともありますし、逆に体調が悪く、免疫力が低下している場合は、ごく少量のウイルスでも発症してしまいます。
また、血液型がB型の人はノロウイルスに感染しにくく、A型の人は感染しやすいという研究報告もあります。

ノロウイルスが怖いけど、牡蠣が食べたいという場合は、必ず加熱して食べるようにしましょう。
厚生労働省によると、食品の中心部分が85度以上で1分間加熱すれば、ノロウイルスは死滅するそうです。
また、加熱調理する場合も、生の状態の牡蠣を扱ったまな板や包丁などの調理器具は、熱湯消毒をするか次亜塩素酸ナトリウム(ミルトンなど)で消毒するようにしましょう。

|
|
|
| インフルエンザ検査→ |
|
|
|
Copyright(C) これであなたも医の達人 All Rights Reserved. |
|



