    |
|
ホーム>感染症情報>ESBL産生菌
|
|
 |
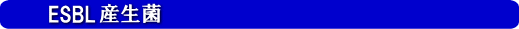 |
|
ESBLとはExtended-Spectrum β-Lactamaseの略で、日本語では「基質特異性拡張型ベータラクタマーゼ」と訳されます。ESBL産生菌とは、「基質特異性拡張型ベータラクタマーゼ」を作り出す細菌のことです。
「基質特異性拡張型ベータラクタマーゼ」とは何でしょう?抗生剤には、βラクタム環という基本構造を持つものがあります。「基質特異性拡張型ベータラクタマーゼ」とは、βラクタム環を分解する細菌酵素ですので、「基質特異性拡張型ベータラクタマーゼ」を作り出すESBL産生菌は、βラクタム環を分解して抗生剤の効果をなくしてしまうのです。つまり、ESBL産生菌は多くの抗生剤に耐性を持つ菌なのです。
ESBL産生菌は1983年にヨーロッパで初めて発見され、1995年には日本でも検出されるようになり、その検出数は年々増加傾向にあります。ESBL産生菌は、院内感染を起こす代表的な細菌であるため、今後の感染拡大に注意が必要です。

東京都感染症情報センターの調査によると、ESBL産生菌は健康な人の糞便から2%前後検出されます。健康な人の場合、ESBL産生菌を保有していても特に健康上の問題はありませんが、免疫力が低下している人の場合は感染症を発症します。
ESBL産生菌が引き起こす病気には、肺炎や尿路感染症、手術創部への感染などがあります。肺炎を起こせば、咳や痰、呼吸困難感、発熱などの症状が出て、尿路感染症を発症すれば発熱や排尿痛、頻尿、腰痛などが主な症状ですが、最悪の場合腎不全を引き起こすこともあります。
そして、ESBL産生菌が血液内に入れば菌血症を引き起こしますが、菌血症になると敗血症ショック(エンドトキシンショック)を起こし、血圧低下や循環不全から多臓器不全に移行し、死亡することもあります。

ESBL産生菌の感染の多くは、病院内の中でもICUやCCUなど集中治療室で起こります。集中治療室は、免疫力が低下していて、感染経路となるカテーテル類が複数挿入されている患者が多いためです。
ESBL産生菌に感染症を発症したら、ESBL産生菌に感受性のある抗生剤を使用することが基本となりますが、それと同時に免疫力を下げている原因の基礎疾患の治療や免疫機能の向上、栄養状態の改善なども行われます。
また、カテーテル挿入部からESBL産生菌が検出されるなどカテーテル挿入が原因での感染は、カテーテルを抜去することで治癒が早まることもあります。

ESBL産生菌は、基質特異性拡張型ベータラクタマーゼという抗生剤を無効化する酵素を産生しますので、多くの抗生剤に耐性を持っています。
ペニシリン系や第三世代セフェム系や第四世代セフェム系など、病院で頻繁に使用する抗生剤は感受性が低く、ほとんど効果がありません。
現在のところ、ESBL産生菌に有効な抗生剤はカルバペネム系です。そのため、ESBL産生菌が検出された場合、第一選択としてカルバペネム系の抗生剤(チエナムやカルベニンなど)を使用します。
しかし、カルバペネム系の抗生剤はESBL産生菌には効果がありますが、院内感染の原因菌の一つである緑膿菌には感受性が低いという性質があります。そのため、院内感染でESBL産生菌が広まり、カルバペネム系の抗生剤を使用すると、緑膿菌が増加してしまうという問題がありますので、まずはESBL産生菌の院内感染を防ぐことが重要です。

ESBL産生菌は、免疫力が低下している人が感染し、多くの抗生剤に耐性を持っているため、院内感染の原因菌となっています。病院内でESBL産生菌の感染症が発症すると、医療職者や医療器具を介して、他の患者に感染が広がってしまうため、院内での感染対策が非常に重要となります。
ESBL産生菌の感染対策は、標準予防策(スタンダードプレコーション)と接触感染予防策を並行して行います。
標準予防策は、体液全てを感染源として扱い、頻回な手洗いや手指消毒、マスクや手袋を着用することです。
接触感染予防策では、ESBL産生菌が検出された患者はできる限り個室に隔離したり、患者に触れるときはガウンやエプロンを着用するようにします。

ESBL産生菌は医療職者を介して感染が広がりますが、医療器具を介して広がることもありますので、医療器具をしっかり消毒する必要があります。
ESBL産生菌はアルコールに弱い性質がありますので、血圧計や体温計などほかの患者と共同で使用するものは、使用するたびにアルコールで清拭して消毒して感染拡大防止に努めます。また、ベッド柵など患者周囲の物品もアルコール消毒しておくと良いでしょう。

|
|
|
| 最新ノロウイルス情報→ |
|
|
|
Copyright(C) これであなたも医の達人 All Rights Reserved. |
|



