    |
|
ホーム>感染症情報>エボラ出血熱の常識
|
|
 |
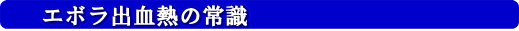 |
|
2013年12月に西アフリカのギニアで発生したエボラ出血熱の流行は、ギニア、リベリア、シエラレオネの3ヶ国にとどまらず、欧米にも広がりを見せています。2014年10月25日現在で感染者は1万141人、死者は4922人に上っていて、世界的な脅威となっています。
エボラ出血熱は、エボラウイルスというRNAウイルスが原因の感染症です。エボラウイルスが初めて確認されたのは、1976年の南スーダンです。この時は284人が感染し151人が死亡しました。
最初の感染者の出身地近くのエボラ川の名前を取って、「エボラウイルス」、「エボラ出血熱」と名づけられました。
この流行後は、約40年間で10回の突発的な流行がアフリカでありましたが、基本的に限局的な流行のみで、流行が複数国に及ぶことはありませんでした。
エボラ出血熱の最も恐ろしい点は、致死率が高いことです。流行を起こすエボラウイルスの株によって致死率は違いますが、60〜80%程度と非常に高くなることが多いんです。最も致死率が高かった流行は2003年のコンゴで起こった流行で、143人が感染128人が死亡で致死率が90%でした。
今回の2014年のエボラ出血熱の致死率は、10月26日時点で1万141人が感染、4922人が死亡ですので、致死率は約48%となっています。今までのエボラ出血熱の流行と比べると、致死率が低いですよね。
今までは致死率が高かったので、患者が感染を広める前に亡くなってしまうため、流行が限局的で済んでいたのですが、今回は致死率が低めのために流行が広がっているのではないかと推測されています。

エボラ出血熱は、症状が出ている患者の血液や汗、唾液などの体液や分泌物、吐瀉物、排泄物などに触れたり、それらに汚染された医療器具などの物質に防護なしで触れることで、エボラウイルスが粘膜や小さな傷口から侵入して感染します。
また、エボラウイルスは患者が死亡した後もしばらく体内で生息していますので、遺体に触れても感染は広がります。西アフリカでは、葬儀で遺体に触れるという習慣があるので、この時に感染が広がったという経緯もあるようです。
エボラウイルスの感染力は非常に強く、たった数個のウイルスが体内に侵入しただけで感染します。ギニアで感染した看護師が患者の看護をしていて、手袋をしたまま汗でずり落ちてきたメガネを押し上げた時に、目や鼻の粘膜からウイルスが侵入して感染したというケースもあるんです。
ただ基本的には、エボラウイルスに感染していても潜伏期間中で症状が出ていない時は感染しませんし、空気感染もしません。
エボラ出血熱の潜伏期間は、2日から21日間となっていて、平均は1週間程度です。汚染された注射器や使用済み針を通した感染では潜伏期間が短くなり、接触感染では長くなる傾向にあります。

エボラ出血熱は平均1週間の潜伏期間を経た後、突発的に発症します。発症直後は、高熱や筋肉痛、頭痛、喉の痛み、脱力感などインフルエンザと似たような症状が現れます。
初期症状だけではインフルエンザとの判別が難しいのに加えて、発症初期は検査をしてもエボラウイルスが検出されずに陰性となってしまうことがあり、感染が拡大する要因となっています。
初期症状が現れた後は、2〜3日で急激に悪化し、嘔吐や下痢、全身の発疹、肝機能や腎機能の異常が現れ、白血球や血小板が減少することで全身の出血傾向が強くなり、口腔や歯肉、鼻腔、消化管などから出血し、下血や吐血などが見られて、多臓器不全を起こして1週間程度で死亡します。
エボラ出血熱は、その名前のイメージから「血だらけになって死ぬ」、「全身の毛穴から出血して死ぬ」と思われがちですが、実際は皮下出血や鼻血、歯茎からの出血はあるものの、下血や吐血は末期になって重症化すると起こる程度で、嘔吐や下痢の症状のほうが強いことが多いようです。

|
|
|
| 最新ノロウイルス情報→ |
|
|
|
Copyright(C) これであなたも医の達人 All Rights Reserved. |
|



