    |
|
ホーム>感染症情報>偽膜性大腸炎
|
|
 |
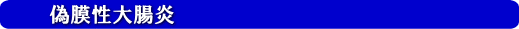 |
|
人間の腸内には、様々な細菌が住んでいます。「善玉菌」や「悪玉菌」という言葉を聞いたことがあると思いますが、これは腸内細菌のことです。また、最近注目が集まっている乳酸菌も腸内細菌の一種ですね。
健康な人の場合、この腸内細菌がバランスを保って生息して、それぞれ働いていることで、栄養分の吸収や便の排泄、免疫機能の強化などに役立ち、健康状態を維持しています。
ところが、病気の治療のために抗生物質を使用したことで、その抗生物質の作用で特定の腸内細菌が減少し、逆にある種の菌が異常に増殖してしまい、腸内細菌のバランスが崩れてしまうことがあります。これを「菌交代現象」と呼んでいます。
この菌交代現象によって、増殖した菌が原因で大腸に炎症が起こり、大腸の壁に偽膜と呼ばれる小さな円形の黄白色の膜が作られます。この病態が、偽膜性大腸炎です。

偽膜性大腸炎の原因は、抗生物質の使用です。感染症にかかったり、手術後などは長期間にわたって抗生物質を使いますが、この抗生物質の使用によって、菌交代現象が起こり、大腸内にクロストリジウム・ディフィシルという菌が異常増殖します。このクロストリジウム・ディフィシルが偽膜性大腸炎を引き起こします。
クロストリジウム・ディフィシルは、多くの抗生物質に耐性を持っている菌です。そのため、他の腸内細菌が抗生物質の作用で減少しても、クロストリジウム・ディフィシルは耐性を持っているため減少せず、むしろ増殖することができるのです。
このクロストリジウム・ディフィシルが出す毒素が大腸の粘膜の循環障害を生じさせることで、小さな円形の偽膜が形成され、様々な症状を引き起こします。

偽膜性大腸炎の主な症状は下痢です。下痢の中に粘液や血液が混じっていたり、腹痛や吐き気、発熱、腹部の張りなどの症状が伴う場合もあります。
偽膜性大腸炎は、抗生物質の使用後1〜2週間で発症することが多いので、抗生物質使用後1〜2週間で上記のような症状が出た場合は、放置せずに、すぐに医師や薬剤師に報告するようにしましょう。
偽膜性大腸炎を放置すると、脱水や電解質異常をきたし、重症化すると死に至ることもありますので、「単なる下痢」と思わずに、早期に適切な治療を受けることが重要です。

偽膜性大腸炎の疑いがある場合、便の培養と便中にクロストリジウム・ディフィシル菌の毒素(CDトキシン)が検出されるかどうかを検査します。
また、偽膜性大腸炎の主症状は下痢であるため、他の下痢を主症状とする疾患との判別が難しいため、内視鏡検査をして、円形で黄白色の小さな偽膜が大腸の粘膜に作られているかどうかを確認することもあります。
偽膜性大腸炎は直腸かS状結腸が好発部位ですので、内視鏡検査をすれば90%以上が診断可能になります。

偽膜性大腸炎の原因は抗生物質の使用ですので、抗生物質使用中に偽膜性大腸炎を発症した場合は、抗生物質の使用を中止します。
抗生物質の使用後に発症した場合は、基本的に対症療法のみとなります。輸液をして下痢による脱水を予防したり、乳酸菌製剤を投与して腸内細菌のバランスを整えるなどの治療法が行われます。
通常は、対症療法のみで回復していきますが、重症化した場合はクロストリジウム・ディフィシルに有効なバンコマイシンという抗生物質を投与することがあります。

偽膜性大腸炎は、クロストリジウム・ディフィシルという菌が異常増殖した感染性大腸炎です。つまり、感染症の一種と言えるのです。
実際に、偽膜性大腸炎は院内感染で起こる主な病気の一つで、12日間入院すれば21%の人がクロストリジウム・ディフィシルに感染して、感染した人の37%が発症し、偽膜性大腸炎を発症した人と同部屋に入院していた場合、49%が便培養で陽性となるという研究データがあります。
この感染は経口感染ですので、手洗いの励行が有効な予防策となります。もし、自分が入院することになったり、ご家族が入院して面会に行く時は、手洗いを意識的に行って、院内感染を予防するようにしましょう。

|
|
|
| 最新ノロウイルス情報→ |
|
|
|
Copyright(C) これであなたも医の達人 All Rights Reserved. |
|



